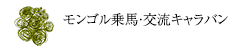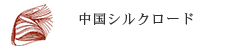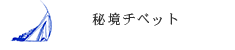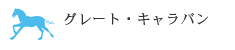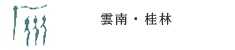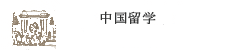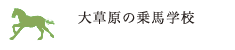旅の記憶

「永遠なるものとはなにか、それは人間の記憶である。」
乗馬キャラバン隊長 張 宇
 半年前、モンゴルへ旅したときの話である。
半年前、モンゴルへ旅したときの話である。
大草原の駿馬、モンゴルの人々は、今もなお鮮やかに浮かんでくる。
帰ってきてからも、人々の唄はずっと耳の中にとぎれることなく聞こえつづけていた。
それほど美しかった。それほど、魂魄のこもった唄だった。
唄を聴いていると、馬のリズムに合わせたその抑揚に、
いつしか草原の霞のなかを疾走している自分がまざまざと蘇えってくる。
北京から列車でモンゴルに入る。
距離はさほどではなかったが、その夜、万里の長城をどこかで越えるのだ。
深夜になっても、ほとんどの人が眠れなかったようだ。
草原の匂いを我先にかいでみたかった。
次第にあたりは静かになり、列車の、大草原をひた走る音だけが闇を包んでいる。
皆は胸に何かが潜んでいるように息をしずめていた。誰かが沈黙をやぶった。
『星をみて』
モンゴルの星を思いうかべるとき、私はその天から落ちてくるような、
手を伸ばせばすぐにも届きそうな姿に威圧される。
遊牧民が太古の昔から住んでいた住居、ゲル。
星空はさながらゲルにつるされた宝石だ。
長らく憧れていた、美しい星空。それがこんなにも近くに現れてくるとは。
私は身がひきしまるのを覚えた。まるで長年の夢を突然に叶えたように。
そのとき星々に抱いた感情は、畏敬以外の何物でもなかった。
モンゴルの民は青いハタをもち、唄を歌いながら酒をつぐ。
五十度もある強い酒であった。
草原に来る人々への心からのもてなしである。
歌いつづけられて勧められては、飲まないわけにはいかない。
草原では、装飾も、遠慮もいらない。
モンゴル人と出会って、そのことをあらためて感じた。
彼等の酒好きは、酒交じりの話を好むというものではなかった。
彼等は酒そのものを好んでいた。
モンゴル人の話は明快そのものである。
褒め言葉は、韻を踏んだ即興詩でなければならない。
そしてその目は、鷲の目のように遠くを見すえている。
未来と過去をも同時に見すえているかのようだ。
草原には、固有に馬がいた。
モンゴル人にとってモンゴル馬はこよなき友で、
他の国の競馬場で走っている馬など、
彼等にいわせると、改良されすぎて、いわばめかしすぎて、
賢さが薄らいでいるそうである。それに情も薄いという。
それに比べてモンゴル馬は良質の酪製品のように情に厚く、その心は神秘的だと言う。
草原に年一度ナーダムと名づけられた祭りが行われる。馬たちの祭りでもある。
少年少女が騎手になり、無数の馬が、三、四十キロのコースを一気に駆けるのである。
決勝点に飛び込んで息絶えて死ぬ馬もしばしばあると聞く。
なるほど、馬ほど人間に篤い動物はないと感嘆した。
十三世紀のチンギス・ハーンの大遠征を可能にしたのはこの種の馬だと思えば、
馬格が小さい割には、すさまじい器量である。
遊牧民の生活はお世辞にも華やかなものとはいえない。
食べるは牛と羊だけ、飲むのはミルク酒と茶だけである。
草原を発つ日の朝、雨が降り始めた。7月とは思えないほどの寒さだった。
私は同じパオにいる人からジャケットを借りて、なんとか耐えぬいたが、
遊牧民の暮らしとは、この嵐に立ち向かう度胸そのものではないだろうか。
なぜ人々はこれほどにつよく生きていけるのか。
そして、なぜ欲望のために死ぬのであろうか。
私は嵐の中に考えてみたかった。
半年前、私はモンゴルの大草原にいた。
生きていてよかったと思った。
それは私の心のどこかに隠れていた空虚と卑屈を一掃され、
すべてを許す気分になれたからである。